令和7年度 安衛法
択一式
○【問8】= 労働安全衛生に関する問題:
▶労働安全衛生に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、Cにおける「電子情報処理組織」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
・【令和7年問8A】(一部補正)
労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。
・【令和7年問8B】(一部補正)
労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。
・【令和7年問8C】 【直近の改正事項】
労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。
労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。
労働安全衛生規則第12条の3第1項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。
○【問9】= 就業制限に関する問題:
▶労働安全衛生法に定める就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、選択肢A、C及びDにおける「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。
事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
○【問10】= 作業環境測定の実施頻度に関する問題:
▶労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
事業者は、労働安全衛生規則第558条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
選択式
総評
選択式は、2つの空欄であり、「作業管理」についての出題と、特定機械等以外の機械等の譲渡等の制限(安衛法第42条)についての出題でした(労基法のこちら以下)。
いずれも簡単ではなく、この2つの空欄とも正解できないという危険性がありました。
択一式は、【問8】を正解する必要があり、その他の2問は正解することは困難でした。
まず、【問8】(こちら)は、正解肢が分かりやすいため、正答する必要があります。
肢のA(こちら)は、「建設工事の注文者等の責務」(第3条第3項)からの出題であり、B(こちら)は、「元方事業者の講ずべき措置等」のうち「指導」(第29条第1項)からの出題であり、いずれも、それらの規定の適用範囲を問うものですが、実は、いずれも、翌年度の試験対象となる改正事項が含まれる規定から出題されたものです(特にAについては、改正の原因となる箇所が論点となっています)。
ただし、このA及びBは、確実な知識がなくても、設問を丁寧に読めば正答することは可能です(Bについては、過去問もあります)。
C(こちら)は、令和7年1月1日施行の直近の改正事項から出題されました。改正事項をマークされていた場合は、正答が容易でした。
D(こちら)は、巡視に関する衛生管理者と産業医との比較に関する出題ですが、基礎的な知識であり、正答必須です。
E(こちら)は、安全衛生推進者に関する専属性・専任性の問題です。ややマイナーな論点ですが(専属性については、【平成15年問10B(こちら)】で出題があります)、正解肢が分かりやすいため、正誤には影響しないでしょう。
【問9】(こちら)は、就業制限に関する出題であり、肢Aが平成28年の過去問において出題されていましたが、これを含めても難しい内容であり、正解することは厳しかったです。
【問10】(こちら)は、作業環境測定の実施頻度に関する出題であり、当サイトではこちらの表ですべての記載がありましたが、しかし、正解することが困難でした。
作業環境測定の実施頻度(測定回数)については、基本的に、「6月以内ごとに1回、定期に」が多いため、(余裕がある場合は)それ以外を押さえておくとよいです。
労基法・安衛法の選択式については、労基法で2点しか確保できない場合に、安衛法で1点確保できるかが鍵になります。
従って、安衛法の選択式対策は重視する必要があり、テキストのキーワード・数字を記憶する必要があります。
択一式についても、1点は確保できるように、出題頻度が多い安全衛生管理体制・健康診断などを中心に、当サイトを始めとする基本テキストを十分読み込んで頂く必要があります。
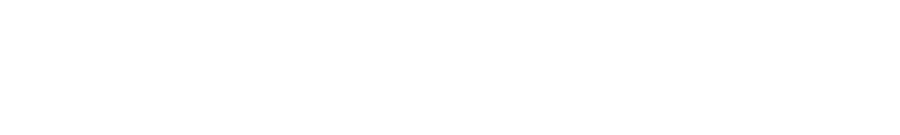
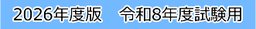 講義 社労士合格ゼミナール
講義 社労士合格ゼミナール