【令和8年度版】
令和8年度版 更新等のお知らせ
令和7年8月27日(水曜日)
本試験、大変お疲れさまでした。
今回、選択式について分析します。
実力のある方でも、いずれかの科目で基準点を下回る危険性があるような出題内容となっていました。
では、さっそく科目ごとにみます。長文となり、恐縮です。
〇選択式
〔1〕労基法・安衛法
労基法・安衛法は、安衛法の2つの空欄が結構難しく、労基法の3つの空欄を正解する必要があります。労基法の空欄Cを正解することができたかどうかが合否の分かれ目となりそうです。
なお、労基法・安衛法の選択式は、このように安衛法の2つの空欄が難しいケースが少なくなく、その意味で、労基法の選択式の対策、特に判例対策が重要となります。
1 問1は、付加金制度の概要についての出題です。割合基本的な出題であり、条文問題といってよいです。
学習歴の短い方などは、この設問が付加金について出題されていることを把握すること自体が難しかったかもしれません。
付加金に関する出題であることを把握するキーワードとしては、設問中に、「労働基準法第114条」とあること(労基法の後ろの方の条文であるということです)、「同法第37条の規定に違反した使用者に対して」「支払を命ずることができる」とあること(第37条が割増賃金の規定であることが自然に思い出せる程度に学習する必要があります)などが挙げられます。
使用者に対して支払いを命ずる制度なのですから、やはり付加金という連想が出てくるところです。
労基法の場合は、法条文が少ないですから、条文をベースに学習しますと、本問のような条文問題に対応しやすいです。
ちなみに、当サイトの直前対策講座では、こちら(直前対策講座のパスワード)の【問4】で付加金に関する最高裁判例を取り上げていました。
2 問2は、【東朋学園事件=最判平成15.12.4】からの出題です(労基法のこちら。労基法のパスワード)。
いわゆる「権利行使抑制法理」を採用している判例であり、この法理については、労基法の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いに関する【沼津交通事件=最判平成5.6.25】がリーディングケースです(労基法のこちら以下)。
権利行使抑制法理とは、「当該権利の行使を抑制し、ひいては法が労働者に当該権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるときに、当該措置は、公序(民法第90条)に反するものとして無効となる」とする旨の判例法理です。
この「権利行使抑制法理」については、当サイトでも色々な箇所で取り上げており、特にマタニティ・ハラスメントに関する【広島中央保健生協事件 = 最判平成26.10.23】との関係(こちら)について強い関心を持っていました。
空欄のCは、この法理の上記太字に相当する箇所が出題されたものです。
この東朋学園事件判決は、平成22年度の選択式において、「公序に反するもの」という箇所が空欄とされました(今回の空欄Cの直後の部分です)。
テキストによっては、労基法の産前産後休業の箇所で、この東朋学園事件判決に言及されていないものもありそうでして、市販の1冊本のみを使用している方などは、今回の出題が初見だったということもありえます。初見ですと、正答がやや難しくなりますが、選択肢にそれほど紛らわしいものはないため、結果的には正答することが可能だったかもしれません。
なお、「権利行使抑制法理」を採用している判例は、いくつかあり(前掲のリンク参考)、【日本シェーリング事件=最判平成元.12.14】(賃上げの対象となる稼働率の算定にあたり年休等の休業期間を除外した労働協約の適法性が争われたもの)は労基法の【平成23年問6C(こちらの下部)】で出題されています。
労働法の判例については、当サイトでもこちらで目次を作っていますので、時間があるときにでも、少しずつ判例に目を通して頂ければと思います(今年度は、労働組合法の判例の目次も作ります)。
3 問3は、少し難しいです。
もっとも、一般に、職場における労働者の健康の保持増進を図るためには、①「作業環境の管理」、②「作業の管理」、及び③「健康の管理」といういわゆる「労働衛生の3管理」が適切に実施されることが必要とされており(安衛法のこちら。安衛法のパスワード)、空欄のDには上記②の「作業の管理」が対応します。
この労働衛生の3管理については、【選択式 平成29年度(こちら)】で「健康管理」に関連して出題されています(空欄とはされませんでしたが)。
4 問4は、特定機械等以外の機械等の譲渡等の制限(第42条)に関する出題です(こちら以下)。
第43条の局所防護装置(こちら)については、平成22年度の選択式(こちら)で出題されているのですが、今回の第42条については初めて選択式で出題されたようです。
当サイトでは、一応、ゴロによる記憶をご紹介してありました(前掲のリンク先参考)。
この問4については、選択肢の中に紛らわしいものが多く(⑧「譲渡し、展示し」、⑭「販売し、賃貸し」、⑮「販売し、販売のために展示し」)、正解が厳しかったかもしれません。
「譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない」というのは、上述の第43条の局所防護措置のケースです。
次に、労災保険法です。
〔2〕労災保険法
労災保険法は、空欄のC(長期家族介護者援護金)の正答が難しく、その他の4つの空欄から3つを正解する必要があります。
1 問1は、遺族補償年金の障害要件についての出題です。施行規則第15条からです(こちら。労災保険法のパスワード)。
割合基本的な問題なのですが(ユーキャンなどの1冊本でも記載があります)、空欄Bについては、選択肢に⑬「日常生活」や⑳「労働又は社会生活」といった紛らわしいものがあり、少々迷った方もおられるかもしれません。
これについては、障害(補償)等給付における障害等級の考え方(こちら以下)が参考になります。
即ち、このリンク先の下部で記載していますように、労災保険法の場合、障害等級は、労働能力の喪失の程度(労働の可能性の程度)により細分化されています。労災保険法は、労働者を主な保護対象としているため、障害等級も労働の可能性の程度を基準としていることになります。
対して、国民年金の障害基礎年金の場合は、全国民に共通する強制加入である公的年金制度としての性格から(即ち、労働者・被用者だけでなく、非被用者も対象となっています)、障害等級も日常生活の制限の程度という観点が重視されています。
この点を思い出して頂くと、空欄のBには、「労働」が入り、「日常生活」とか「社会生活」は入らないと連想可能です。
労災保険法は、この空欄A及びBのいずれも正解しませんと、3点を確保することが難しくなるかもしれません。
2 問2は、前述の通り、正解することが難しいです。
「長期家族介護者援護金」という「社会復帰促進等事業」の中の「被災労働者等援護事業」からの出題であり、当サイトではこちらで記載していますが、通常は学習しない箇所ですので、正解は無理でしょう。
ただし、今後は、社会復帰促進等事業のうちの各事業についても、数字関係は見ておく必要が生じました。
3 問3は、労災就学援護費の決定の行政処分性が問題となった【最判平成15.9.4】からの出題です。
この判例は、行政法上は有名な判決です。当サイトでは、こちら以下で詳述しています。
この問3では、行政法上の論点ではない部分が出題されています。
空欄のDは、判決文ではさほど注意せずに読み過ごしてしまう箇所ですが、労災就学援護費と保険給付との関係について問うものですから、選択肢からは、⑪「代替」、⑮「付加」、⑯「補完」あたりが候補となります。
保険給付に「付加」して支給されるのは「特別支給金」であり、労災就学援護費は、それに対応する保険給付が存在しませんから、⑮「付加」ではなく、⑯「補完」が正解となります。
⑪「代替」では、労災就学援護費が支給される代わりに保険給付が支給されなくなるといった意味合いになりますから、ふさわしくありません。
空欄のEについては、労災就学援護費の支給に関する事務は所轄労働基準監督署長が行うということは、そこそこ重要な知識であり、こちら(の(B))で学習しています(こちらやこちらの図も参考です)。
保険給付や特別支給金の場合と同じであると押さえておきます。
〔3〕雇用保険法
雇用保険法も、微妙です。正確な知識がないと、空欄のB、D、Eなどで落とす可能性があり、楽に基準点を上回ることができるとは言いにくい内容です。
1 問1は、目的条文(第1条)からの出題であり、今回、令和7年4月1日施行の改正により、「育児時短就業給付」(及び「出生後休業支援給付」)が新設されたことに伴い改められているため、同条が出題されることを想定しておく必要がありました(こちら)。
当サイトでも、空欄のAの部分については、直前対策講座のこちらで取り上げていました。
改正箇所を含む空欄Aよりも、Bの方が厄介だったかもしれません。
この空欄Bの部分は、雇用保険二事業について言及した部分ですから、雇用安定事業と能力開発事業に対応したものです。空欄B自体は、前者の雇用安定事業に関するものであり、雇用の安定のためには、まずは「失業の予防」が重要なのであり、このような観点から正解に達することができます。
目的条文については、どの科目についても、常に出題される可能性があると考えて、暇を見ては熟読して頂き、重要なキーワードを暗記してしまうのが良いです。
2 問2は、高年齢求職者給付金の受給手続からの出題です。
第37条の4第5項(雇用保険法のパスワード)の条文通りの出題です。当サイトではこちらです。
①出頭して、②求職の申込みをして、③失業の認定を受ける、という手続の流れは、基本手当の場合と同じです(こちら以下)。
3 問3は、日雇労働求職者給付金の特例給付の要件に関する出題です。
ややマイナーな箇所からの出題ですので、侮れません。
特例給付に関する出題であることは、「継続する6月間」、「各月11日分」とあるところから把握します。
この「6月」という数字については、平成23年度の選択式で問われています(こちら)。
空欄Eについては、当サイトでは、ゴロ合わせで押さえていましたので、サービス問題ですが、覚えていないとお手上げになるところです。
以上、雇用保険法は、条文からの出題で占められており、その他の科目も含め、条文をチェックしながら、知識を整理し、かつ、ゴロ合わせ等で数字等を記憶するという作業が重要なことがわかります。
〔4〕労働一般
労働一般は、労働経済のデータに関する出題が(2つだけの空欄ではありますが)復活してしまい(空欄のA、B)、その他の空欄3つを正解する必要があります。
しかし、空欄のD及びEは、労働組合法の判例からの出題であり、厳しく感じた方が多かったかと思います。基準点が下がるかもしれません。
以下、各設問を見ます。
1 問1は、総務省の「統計からみた我が国の高齢者」という資料(こちらの9頁)からであり、これは私もチェックしたことがありませんでした。
今回の出題は、65歳以上の就業者の産業別の数・割合をテーマとしています。
ちなみに、もとになるデータは、労働力調査(基本調査)であり、令和6年版労働力調査のこちらで判明します(わかりにくいため読まないで結構なのですが、上段の「年齢階級」の箇所を「65歳以上」に変えて、縦軸「2023年」(令和5年)の箇所を見ると、データが表示されます。令和6年版の労働力調査の本編(白書対策講座のこちら以下)では、「65歳以上の就業者の産業別」のデータは掲載されていませんが、前掲のリンク先の方で掲載されています)。
通常は、「統計からみた我が国の高齢者」を読み込んでいる人はいないでしょうから、本問は既存の知識と常識によって判断することとなります。
65歳以上の就業者の産業別の数ですが、トップが「卸売業、小売業」で、2番目が空欄となっています(A)。
2番目であることと、Aは10年前の2.4倍の増加となっていることから、選択肢を参考に正解を導きます。
選択肢としては、②「医療、福祉」、③「運輸業、郵便業」、⑩「建設業」、⑬「宿泊業、飲食サービス業」、⑭「生活関連サービス業、娯楽業」、⑮「製造業」、⑰「農業、林業」及び⑱「不動産業、物品賃貸業」が候補です。
この空欄Aは、判断が難しいです。
そこで、空欄のBも見ますと、Bは、(ⅰ)各産業の就業者に占める65歳以上の割合が最も高いのに、(ⅱ)10年前と比べて3万人減少しているという産業です。
この(ⅰ)と(ⅱ)の2つの条件を満たす産業を上記の選択肢の中から探しますと、やはり、⑰「農業、林業」が匂う(いい香り)となりそうです。
空欄Aに戻りますと、⑬「宿泊業、飲食サービス業」あたりも臭う(くさい香り)のですが、正解は②「医療、福祉」です。言われてみれば、その通りかなという感じはしますが、正解することは厳しそうです。
この問1は、空欄のAもBも落とす可能性があります(Bは正解し得る余地がありますが)。
2 問2は、労働施策総合推進法の「職場におけるパワーハラスメント防止措置等」から、その要件に関する問題(第30条の2第1項。労働一般のパスワード)です。
これは、落とせません。当サイトでは、こちらの下部の図を参照です(図中の②です)。
このパワハラ防止対策については、令和2年6月1日の改正施行で創設され、施行直後の令和3年度の択一式で1肢出題がありましたが(経過措置に関する出題。こちら)、今回、2回目の出題で選択式として狙われました。
ただ、本問は、パワハラの要件ですから、必ず学習する箇所といえますし、出題もそのうちありうるだろうと事前準備もできたところですので、正解することは比較的容易だったと思います。
3 問3は、労働組合の集会のための食堂の使用拒否が支配介入の不当労働行為に該当するか問題となった【オリエンタルモーター事件=最判平成7.9.8】からです。
2年連続、労働一般の選択式は、労働組合法の判例からの出題となりました(前年は、労働協約の事業場単位の一般的拘束力(労組法第17条)に関する【朝日火災海上(高田)事件=最判平成8.3.26】でした。こちら)。
今回のオリエンタルモーター事件判決についても、初見の場合は厳しいことになります。
ただし、当サイトでまめに学習されている方は、少なくとも空欄のD(施設管理権)はサービス問題とすることが可能です。
即ち、当サイトでは、労基法の懲戒処分の箇所で、【国鉄札幌運転区事件=最判昭54.10.30】という判決を掲載しており(労基法のこちら)、その解説中で、使用者の施設管理権と組合員の組合活動権(ビラ貼り)との調整が問題となっていることを挙げ、詳細については、労働組合法の組合活動の個所(こちら以下(労働一般のパスワード))で学習する旨を記載しています(オリエンタルモーター事件判決については、前掲のリンク先の下部の労働一般のこちら)。
この施設管理権と組合活動権との調整という論点は、労働組合法における重要かつ基本的な論点です。
このような前提知識が多少ありますと、今回の空欄Dのように、無許可で会社の食堂を使用したことによって会社の「 D 権」が無視されたという文脈では、「施設管理権」がすぐ連想されることになります。
空欄のEについては、微妙ですが、不当労働行為に関する判例や労働委員会の救済命令等において、「組合の弱体化を図る」といった文言はしばしば用いられており、使用者の「不当労働行為の意思」を示すひとつの例として言及されることが少なくないです。
つまり、不当労働行為の要件において、一般には不当労働行為の意思が必要とされることが多く、その意思の存否の判断の際には、使用者に「組合の弱体化を図る」意思、組合に対する嫌悪の意思、反組合的な意思等が認められるかどうかが考慮されることが多いです。
その意味で、組合の弱体化を図る意思は、よく用いられる決め台詞の一つとなっています(例えば、古くは、不当労働行為の意思に関する【大浜炭鉱事件=最判昭和24.4.23】(こちら。労働一般のパスワード)で言及されており、また、複数組合が併存する場合における誠実交渉義務・中立保持義務が問題となった【日本メール・オーダー事件=最判昭和59.5.29】(こちら以下の(一))などでも言及されています)。
このように、当サイトで不当労働行為等の労働組合法を学習された方にとっては、空欄Eも難しくはないのですが、通常は難しい箇所であるといえます。
なお、今回の労働組合法のオリエンタルモーター事件判決のように、労働組合法の判例については、個別の判例ごとをチェックする学習をしても、学習効率は良くないことが多いです。
「抽象化(理論)➡具体化(判例)」という流れ(演繹法)で、抽象的な理論を知ったうえで、具体的な判例でその理論の活用の仕方を押さえると効率的です。
例えば、オリエンタルモーター事件判決の場合は、そもそもは、労働組合の組合活動の正当性(適法性)が問題となっているのであり(その判断基準はこちらです)、そのうえで、その正当性を判断する要素の一つである手段・態様についてこちらが問題となり、ここで「使用者の施設管理権」(は保護されなければならない)という組合活動の限界の問題が生じてくるという構造になっています。
そして、使用者の施設管理権と組合活動との調整(前掲のこちら)に関する代表的な判例(リーディングケース)が、「ビラ貼り」の正当性が問題となった【国鉄札幌運転区事件=最判昭和54.10.30】(前掲のこちら)であり、他方、「組合の集会」の正当性が問題となったのが、本件の日本メール・オーダー事件(前掲のこちら)であるということです。
結局、(時間的に許せば)当サイトの労働組合法を読んで頂くのが、労働組合法の判例対策としては最も有効であると考えています(判例だけを掲載して解説したまとめ本のようなものも、便利ではありますが、理論面が弱く、丸暗記で終わり、結局、覚えていないということになりかねません)。
〔5〕社会一般
当サイトの感触では、労働一般よりも、この社会一般の方が「やばい」ようにも見えるのですが、皆様の感触はいかがだったでしょうか。基準点の引き下げになりそうな気もしますが、他方、空欄A、C、D、Eは、「山カン」で正答になる可能性も高そうにも見え、微妙なところです。
1 問1は、令和5年度の「国民年金の加入・保険料納付状況」(こちらの3頁)からの出題です。
保険料の最終納付率が問われていますが、「近年は高い」という大まかなイメージがあると、正答できます。
具体的には、選択肢中の④「98.1」%は高すぎる気がし、②「68.1」%よりは高い気もし、正解は③「83.1」%ということになります。
なお、上記のリンク先の3頁の下部に記載があるように、納付率とは、「納付月数/納付対象月数 ×100(%)」です。
納付対象月数とは、当該年度分の保険料として納付すべき月数のことですが、免除された月数は除くことに注意です(従って、納付率は高くなっているのです。ちなみに、令和4年のデータですと、第1号被保険者(約1,400万人)の40%強は、保険料免除者(約600万人)です。
また、上記の納付月数とは、納付対象月数のうち実際に納付された月数のことです。
最終納付率については、保険料は過去2年分の納付が可能であることから、現年度に過去2年度分の保険料として納付されたものを加えた納付率です。
2 問2は、高齢者医療確保法の「国、地方公共団体、保険者等の責務」(第3条~第6条)からの出題であり、当サイトでマークしてあるところです(社会一般のこちら以下)。
次の国と地方の対応関係になっています。
①第3条 = 国の責務 ➡ 「国は、国民の高齢期における・・・、各般の措置を講ずる・・・」
②第4条 = 地方公共団体の責務 ➡ 「地方公共団体は、・・・、住民の高齢期における・・・所要の施策を実施しなければならない」
従って、「住民の高齢期」とある空欄のBは、⑮「地方公共団体」が入ります。
この第3条・第4条を学習していない場合は、空欄のBは、「国」と「地方公共団体」との2択となりそうですから、2分の1の確率で正解し得ることとなりそうです。
しかし、この空欄Bについては、択一式の過去問も数回出題がありますので、上記のようなリスクのある状況にならないように、日頃から記憶の仕方を学習していなければならなかったことになります。
「思い出し方を記憶する」ことも、重要な学習です。
3 問3は、介護保険法の第2条第2項(介護保険(保険給付)の基本方針)からです。
空欄Cの「医療との連携」については、択一式の【過去問 平成20年問10A(こちら)】で出題されたことがあります。
知識がなくても、ヤマかんでも当たる可能性はありそうです。
4 問4は、確定給付企業年金法の積立金に関する出題であり、難しかったと思います。
当サイトでは、こちらで記載していますが、選択肢の⑧「最低積立基準額」(こちら)、⑯「積立金の額」(こちら)、⑰「積立上限額」辺りが紛らわしいです。
5 問5は、令和6年版厚生労働白書(こちらの289頁から290頁。pdfの306頁)からです。
これは、かなり厳しい出題です。
私的年金制度に関する改正を決定した空欄のEによって、「①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」のですが、この①と②は、この改正を決定した令和7年年金制度改正法(【令和7.6.20法律第74号。「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」)(遺族年金等の改正を決定した改正法です)の公布日から3年以内の施行であり、③は同5年以内の施行となっています。
つまり、空欄E自体は、令和4年の決定事項なのですが、それに基づき立案された改正法は、本年6月の公布(今回の本試験の適用対象から外れています)であり、前記の①~③も数年先の施行となっています。
素材である令和6年版の厚生労働白書は、すでに昨年8月に刊行されたものであることもあって、空欄Eを出題すること自体は問題ないとはいえども、将来の改正施行事項にかかわっているわけで、このような事項を出題するのは、「反則気味」ではないかと思えます(過去、あまりこのような出題はなかったように記憶しています)。
雰囲気的には、選択肢中の⑨「資産所得倍増プラン」か⑪「所得倍増プラン」が怪しいですが、この令和4年の「私的年金制度」(確定拠出年金及び確定給付企業年金等)等に関する改正を導いたプランは、岸田内閣の下、「貯蓄から投資」という標語で代表される「資産所得倍増プラン」でした。
同プランは、個人が持つ貯蓄を投資にシフトすることを奨励し、国民の資産形成を促進し、所得を増やすための政策でした。
そこで、「所得」に加えて「資産」も含まれる⑨が正解となります。
社会一般は、空欄BとCを正解したうえで、A、D、Eの3つの空欄のうちどれかを山カンで当てるということになりそうです。
今回の出題を見ましても、空欄のB及びCは、総則的な規定からの出題であり、今後も総則的な規定は、キーワードに注視しながら学習する必要があります。
〔6〕健康保険法
健康保険法は、学習している人にとっては簡単なのですが、初学者の方などにとっては、厳しく感じたかもしれません。
1 問1は、出産育児一時金の支給額についてです。
空欄のA(48万8000)及びB(3万)は、当サイトのこちら(健保法のパスワード)の冒頭の通りです(施行令第11条柱書)。
「支給額は、原則48万8千円、産科医療補償制度に加入する病院等による医学的管理の下における出産の場合は1万2千円がプラスされ合計50万円」とだけ覚えておくと、空欄Bの3万円が出てこないため、施行令第11条に規定されている3万円も含めて記憶しておく必要がありました。
空欄Cの「85」日以上は、基本的な知識です(こちら)。
2 問2は、任意適用事業所の任意適用の取消し(こちら以下)に関する出題であり、典型的な論点であるため、比較的容易だったと思います。
当サイトでは、ゴロ合わせで押さえており(こちら)、このゴロで、空欄Dの「4分の3」は埋まります。
空欄のEの任意適用の取消しの認可の申請書の提出先については、当サイトでも、(任意適用の認可の申請書の提出先とともに)結構強調して記載していたのですが(こちら以下)、少々注意です。
即ち、任意適用事業所の任意適用及びその取消しのためには、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です(第31条第1項、第33条第1項)。
ただし、この任意適用事業所の任意適用及びその取消しに係る厚生労働大臣の認可の権限は、協会管掌健保に係る任意適用事業所の場合(即ち、当該事業所が健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)でない場合です)には、機構に委任されており(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任として、第204条第1項第3号)、他方、組合管掌健保に係る任意適用事業所の場合には、地方厚生局長等に委任されています(施行規則第159条第1項第3号)。
そして、施行規則第21条第1項前段や施行規則第22条第1項前段は、これらをまとめて、健康保険任意適用(取消)申請書を「機構又は地方厚生局長等」に提出しなければならない旨を規定しているものです。
そこで、空欄Eも、⑳「日本年金機構又は地方厚生局長」等となります。
この空欄Eは、やや注意ですが、選択肢が「社会保険診療報酬支払基金」とか、「国民健康保険団体連合会」といった関係のなさそうなものばかりであるため、記憶が不正確でも、結果的に正解できそうです。
以上、健保法は、なんとか基準点をクリアできそうです。
〔7〕厚生年金保険法
厚年法は、空欄DとEで迷った方もおられるかもしれません。ただ、定時決定に関する空欄AとBは基本的知識であるため、空欄Cも正解して、基準点をクリアすることは可能です。
1 問1の空欄A及びBは、定時改定に関する基本的な数字についての出題であり、正解することが必要です(当サイトのこちら(厚年法のパスワード)の冒頭の◆の部分で、空欄の数字は全部掲載されています。ゴロ合わせもあります)。
2 問2の空欄Cは、調整期間における再評価率の改定に関する問題であり、割合基礎的な知識です。
「基準年度前再評価率(新規裁定者に係る再評価率)」に関する出題なのか(この場合は、空欄Cは、⑯「名目手取り賃金変動率」です)、それとも、「基準年度以後再評価率(既裁定者に係る再評価率)」に関する問題なのか(この場合は、空欄Cは、「物価変動率」ですが、幸い選択肢には「物価変動率」は存在しません)は問題ですが、設問中に「特別調整率」とあるので、前者の基準年度前再評価率の問題ということになり、空欄Cは⑯「名目手取り賃金変動率」です(「基準年度以後特別調整率」なら、後者の基準年度以後再評価率の問題です。こちらの図の左側の1⃣を参考)。
3 問3は、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間に関する出題です。
3号分割が可能となる期間は、特定期間(特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間)であり、大まかには、婚姻していた期間のうち第3号被保険者であった期間となります(こちら以下)。
そこで、本問では、結婚した平成23年1月から離婚した令和6年12月までが、一応、特定期間となりそうですが(なお、特定期間の末日の属する月は特定期間に係る被保険者期間に算入されないため、離婚等をした月の前月までが特定期間に係る被保険者期間に算入されます。こちら以下)、本問では、特定被保険者である乙が障害厚生年金の受給権者であることに気づく必要があります。
即ち、3号分割標準報酬改定請求のあった日に、特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であって、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となっている場合には、原則として、被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求を行うことはできません(第78条の14第1項ただし書、施行規則第78条の17第1項第1号)。
障害厚生年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬額が低下する結果、その年金額が減額され、障害者である特定被保険者の保護に欠ける恐れがあるためです。本文は、こちらです。
本問では、特定被保険者乙は、令和4年2月の障害認定日に障害等級に該当していますから、この令和4年2月に障害厚生年金の受給権が発生しています。
この障害厚生年金は、その受給権の発生前(以前)の被保険者期間を基礎として受給権が発生していますから、この障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間については、3号分割はできないことになります。
具体的には、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とは、障害認定日の属する月まで(その月以前)なのであり、障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としません(第51条)。本問のキーは、ここでした。老齢厚生年金との違い等について、こちら以下で詳述しています。
そこで、本問では、障害厚生年金の障害認定日の属する月である令和4年2月までが障害厚生年金の額の計算の基礎となるため、同令和4年2月までは3号分割ができないこととなります。
以上については、当サイトでは、こちらの「例外」の部分(図も含む)で言及していました。
考え方を理解しておけば難しくないのですが、初見ですと、難しかったと思います。
「理解」が必要であるという例です。
4 問4は、受給権が発生する障害年金に関する出題です。
要するに、障害厚生年金と障害基礎年金の支給要件を思い出して、本問の事実を当てはめて支給要件の該当性を判断するという設問です。
このようなパターンは、厚年法の令和5年度の選択式問2(こちら)で登場しました。
難しいわけではなく、冷静に支給要件をくまなく思い出し、あてはめるだけです。
(1)まず、障害基礎年金の受給権が発生するかです。
障害基礎年金の支給要件は、次の通りです(国年法のこちら以下(国年法のパスワード))。
①初診日の要件=(ⅰ)初診日において、国民年金の被保険者であるか、(ⅱ)初診日において、国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
②障害認定日の要件=障害認定日において、障害等級(1級又は2級)に該当する程度の障害の状態にあること。
③保険料納付要件= 初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること。
本問では、「保険料滞納期間はない」ため、③は満たします。
また、障害認定日に2級であるため、②も満たします。
①が問題です。
被保険者丙は、初診日(倒れて救急搬送された令和7年8月1日)に厚生年金保険の被保険者ですが、67歳であり、老齢基礎(厚生)年金の支給の繰下げを行うため裁定請求をしていない状態(=「繰下げ待機中」)です。
厚生年金保険の被保険者は、原則として、国民年金の第2号被保険者となりますが、65歳以上の者にあっては、老齢退職年金給付の受給権を有しない者に限ります(国年法のこちら以下)。
本問では、67歳であり、老齢基礎(厚生)年金の支給の繰下げを行うため裁定請求をしていない状態がその受給権を取得しているのか問題です。
この点は、「繰下げ待機中」とは、老齢基礎(厚生)年金の受給権を取得している状態をいうのであって、例えば、10年の受給資格期間を満たさない者が65歳を過ぎて老齢基礎(厚生)年金の裁定請求をしていなくても、これはそもそも裁定請求をする要件及び支給の繰下げをする要件を満たしていないのであり、「繰下げ待機中」とは表現しません。
そこで、本問の被保険者丙は、67歳で老齢基礎(厚生)年金の受給権を取得しているため、国民年金の第2号被保険者となりません。
よって、障害厚生年金の初診日の要件である前記①の(ⅰ)「初診日において、国民年金の被保険者」という要件を満たさないことになります。
また、前記①の(ⅱ)の「初診日において、国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること」の要件についても、被保険者丙は67歳であるため、満たしません。
従って、被保険者丙について、障害基礎年金の受給権は発生しません。
(2)次に、障害厚生年金の受給権が発生するかです。
障害厚生年金の支給要件は、次の通りです。
①初診日の要件=初診日において、厚生年金保険の被保険者であること。
②障害認定日の要件=障害認定日において、障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にあること。
③保険料納付要件=初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること(この保険料納付要件は、障害基礎年金の場合と基本的に同様です)。
本問では、①初診日に障害厚生年金の被保険者であり、②障害認定日において障害等級2級に該当し、③保険料納付要件も満たしますから、障害厚生年金の受給権が発生します。
以上より、選択肢の⑪「障害厚生年金のみである」が正解です。
保険法では、何より、支給要件がすらすら出てくるように記憶することが重要です。
〔8〕国民年金法
最後に国年法です。
問1は、初学者にとっては少し厳しいですが、全体としては、基準点をクリアすることは可能な内容といえます。
1 問1は、保険料額であり、その沿革・歴史的事項に関する出題であったため、最近の受験者の方にとっては難しかったと思います。逆に、我々のように古い人間には、簡単な問題でした。
保険料の基本額は、当サイトのこちらのように、平成17年度(平成16年〔=空欄のA)の年金制度の大改正によります)から、毎年度(4月分から)、280円ずつ(平成29年度のみは240円)引き上げられ、最終的には、平成29年度において16,900円〔=空欄のB〕となって固定されました(保険料水準固定方式)。
さらに、「産前産後期間の保険料免除制度」〔=空欄のC)の費用を賄うため、平成31年4月1日からは、基本額は、100円引き上げられ、17,000円となりました。
空欄のBは、やや難しいように見えますが、現在の基本額である17,000円は記憶しておく必要があり、「保険料を100円引き上げている」のですから、「17,000円ー100円=16900円」が空欄Bであると判明します。
以上は、こちらの表も参考です。一応、こちらにゴロ合わせもあります。
2 問2は、学生納付特例における所得の要件についてです。
令和3年の改正後、いつ出題されてもおかしくない論点でしたが、ついに出ました。当サイトでも、「今後、非常に出題の可能性が高い」と記載していました。
当サイトのこちらの表((5)の箇所)を参考です。
空欄のDとEに逆の数字を入れないことに注意です。
以上、選択式の分析でした。
令和7年7月25日(月曜日)
本試験、大変お疲れ様でした。
本年も、択一式が長文となっており、試験終了後は疲労困憊されたことと思います。
目下、本試験内容の分析中です。終了次第、メールを致します。
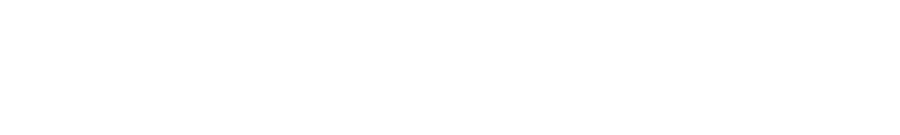
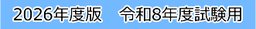 講義 社労士合格ゼミナール
講義 社労士合格ゼミナール